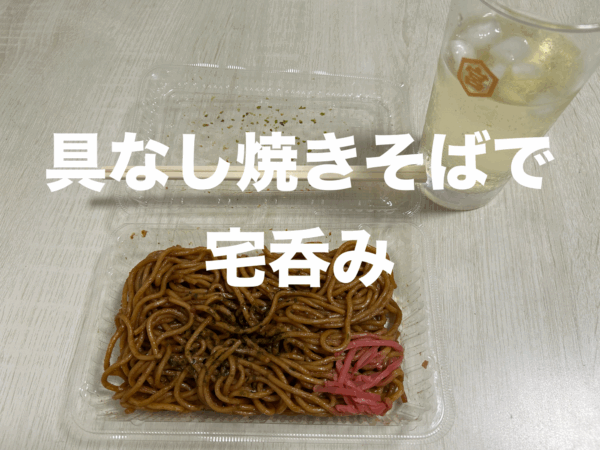最近、気になっているサイバーインシデントについて。
今すぐやる(優先度:高 — まず着手)
1.多要素認証(MFA)を全員に必須化(メール、VPN、管理者アカウント等)。攻撃で最も効く対策の一つです。
2.重要データのオフライン/隔離バックアップを作る(バックアップは定期化・検証・バックアップからの復元テストを必ず実施)。Ransomware対策の基本。
3.脆弱性とパッチ管理の仕組みを確立する(OS・FW・アプリ・ファームウェアを遅滞なく適用する運用フロー)。
4.管理者権限の最小化(Least Privilege)とアカウント分離(日常業務で管理者権限を使わせない)。
5.メール/Webのフィルタリング、アンチウイルス/EDR導入(標的型やマルウェアの初期侵入を減らす)。
30日で整える(短期計画)
1.インシデント対応計画(IR計画)を作る(連絡先、役割、権限、エスカレーション経路、外部通報先を明記)。NISTのインシデントハンドリング原則を参考に。
2.**CSIRT/インシデント窓口の設置(社内担当チーム)**と外部パートナー(JPCERT/CC、警察、セキュリティベンダー、法律顧問)の連絡先一覧を作る。国内インシデントはJPCERT/CCへの相談経路を確保。
3.**ログ収集と監視(SIEMやログの長期保存)**を整備し、異常検知ルールを最低限設定する。
4.**従業員向けセキュリティ教育(フィッシング訓練含む)**を実施。人的ミス防止は重要。
中期(3〜6ヶ月で取り組む)
1.ネットワーク分割(セグメンテーション)とゼロトラスト的制御(重要資産を分離し横移動を防止)。
2.ビジネス継続(BCP)/復旧(DR)計画と復旧目標(RTO/RPO)を定義、復旧手順書と定期的なリハーサルを行う。
3.サプライヤー(クラウド含む)セキュリティ評価と契約上の要件整備(サードパーティ経由の侵害を防ぐ)。
4.**脅威インテリジェンスの受け取り体制(公的機関やベンダーから)**を整備する。
具体的な成果物(テンプレで即作れる)
・インシデント連絡先カード(例:CSIRT代表、CTO、法務、広報、JPCERT連絡先、警察、契約SOC)
・最小権限チェックリスト(管理者アカウント数・サービスアカウント一覧)
・バックアップ検証シート(最終バックアップ日時・復旧テスト結果)
・フィッシング訓練レポート形式(開封率、クリック率、報告率)
初動インシデント対応ワークフロー(短いテンプレ)
1.検知 & 通報:検知者→CSIRTへ報告(時間・検知内容・影響範囲を記録)。
2.一次評価(トリアージ):インシデントの種類(ランサム/漏えい/不正アクセス等)・影響度判定(業務停止・個人情報含むか)。
3.封じ込め(Contain):感染端末隔離、ネットワーク区切り、被害拡大防止のためのACL/VPN切断など。※証拠保全(ログ・イメージ)の優先。
4.根絶 & 復旧(Eradicate & Recover):マルウェア除去、脆弱性修正、バックアップからの復旧、段階的にサービス再開。復旧は事前に定めたRTO/RPOに従う。
5.事後対応(Lessons Learned):原因分析、対策実施、役員と顧客への報告、外部通報(JPCERT/CC・関係当局)を実施。
テーブルトップ演習(必須)
年1回以上、実際に手を動かす模擬演習を。シナリオ:ランサム、顧客データ漏洩、DDoSなど。発見から通知までの時間を計測し改善点を洗い出す。