 Food & Drink
Food & Drink 魚不足につき『快飛(かっとび)』に行ってきた、なんでもない日記。
最近、ラーメンとかラーメンとかラーメンばかりだった(笑)なので魚が不足してると感じ、茅ヶ崎にの『快飛(かっとび)』に行ってきました。刺身天ぷら定食を注文。天ぷら生シラス魚不足と思ったら、茅ヶ崎には『快飛(かっとび)』がある。以上。
 Food & Drink
Food & Drink  Outdoor & Sports
Outdoor & Sports 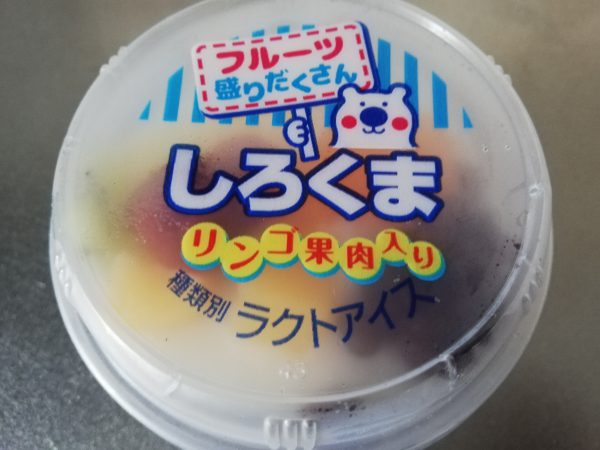 Food & Drink
Food & Drink  Food & Drink
Food & Drink  Life & Design
Life & Design  Food & Drink
Food & Drink  Life & Design
Life & Design  Noodle & Pasta
Noodle & Pasta 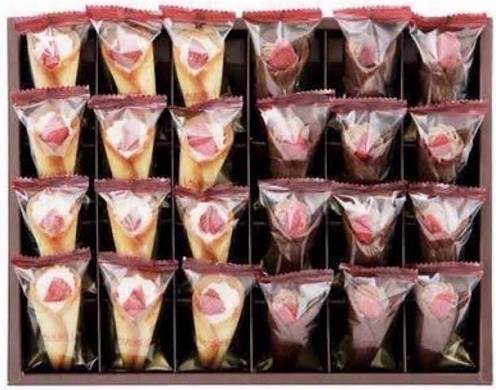 Food & Drink
Food & Drink  Noodle & Pasta
Noodle & Pasta  Life & Design
Life & Design  Craft & Note
Craft & Note